






数多く飾られている
「西さん、頑張ってください! なるべく、なるべく遅く帰ってきてください!」
酒で頬を赤く染めたスーツ姿の中年男性が、西芳照の手を両手で握りしめ、上下に振って力を込めた。
きっとここ数日、「広野町レストラン アルパインローズ」では同じような光景が繰り広げられているのだろう。
西は照れたような笑顔で「ありがとうございます」と頭を下げた。
 アルパインローズは二ツ沼総合公園内に建つふるさと広野館の2階に入っている
店内には日本代表選手のサインやサポーターからのメッセージが書き込まれたユニフォームやボール、色紙が所狭しと飾られている。
アルパインローズは二ツ沼総合公園内に建つふるさと広野館の2階に入っている
店内には日本代表選手のサインやサポーターからのメッセージが書き込まれたユニフォームやボール、色紙が所狭しと飾られている。
西は、サッカーファンの間では全国的に名前を知られる存在だ。2004年から10年間、サッカー日本代表の専属シェフとして海外遠征に帯同し、世界を巡ってきた。僕が広野町を訪ねたのは、西がドイツ、南アフリカに続いて3度目のワールドカップとなるブラジルに旅立つ1週間前のこと。
西の帰国が遅くなるということは、ブラジルで日本代表が勝ち進んでいることを意味する。スーツ姿の男性の「なるべく遅く」という言葉は、日本代表と西への激励だった。
西は男性の連れとも熱い握手を交わしていた。僕はその様子を眺めながら、かつ丼と福島の郷土料理で元日本代表監督のフィリップ・トルシエの気に入り、マミーすいとんを食べていた。かつ丼もマミーすいとんも、口当たりが優しいおふくろの味だった。

西が料理に目覚めたのは、地元福島の高校を卒業後、東京で予備校に通いながら居酒屋でアルバイトをして入る時だった。当初、故郷で居酒屋を開きたいと考ええていた西だが、料理の「奥の深さ」に気付くと、心の奥底に眠っていた探究心に火がつき、いつしか目標が変わった。
「どうせやるなら日本一の料理人になりたい」
一流の料理人を志すようになった西は、「日本料理界の巨匠」とも称される『京料理 よこい』の総料理長・横井清氏のもとで5年間修業。その後、永田町の自民党会館の隣にあった懐石料理店の料理長に就任した。
その店で働いていた96年の年末から年始にかけて、福島に帰省した西に転機が訪れた。
福島県の楢葉町に「でっかいホテル」ができるという話を聞いたのだ。その時35歳、東京で二人の娘を育てていた西は思った。
「自分が生まれ育った町の自然の豊かさや人のおおらかさを知ってほしい」
西はその「でっかいホテル」の求人に応募し、故郷に戻ることを決めた。そのホテルとは、福島県、日本サッカー協会、東京電力がパートナーシップを組んで作った日本初の総合スポーツ施設Jヴィレッジのことだった。
西は施設内のレストラン「アルパインローズ」で働き始め、99年には総料理長に就いた。Jヴィレッジには宿泊施設があり、日本代表も何度か合宿に来たが、「当時、サッカーにはあまり興味がなかったんです」と笑う西にとって、日本代表は特別な存在ではなかった。
そんな西に、日本サッカー協会から日本代表の遠征に帯同できないかとオファーがあったのが04年の3月。同時期、日本の五輪代表選手が遠征先で腹痛に見舞われるというハプニングが起こったため、3月31日にアウェイで開催されるドイツワールドカップ・アジア一次予選のシンガポール戦に向けて、日本代表に帯同してほしいという話だった。
この時、日本代表専属シェフ・西芳照が誕生した。
選手全員のサインが入ったユニフォームが西に贈られた
アルパインローズの名物「マミーすいとん」

西の仕事は選手やスタッフに料理を作ること。一見シンプルながら、やるべきことは多い。ワールドカップの時だけ2人体制になるが、基本的にシェフとして遠征に帯同するのは西ひとり。この10年間、ほとんどの遠征で孤軍奮闘してきた。
ひとりで全員分の食事を作る時間はないので、日本代表が滞在するホテルの料理人の手を借りるのだが、発展途上国への遠征も多く、厨房の衛生状態や設備、料理人たちのレベルはバラバラ。そんな状況で、選手が最高のパフォーマンスを発揮できるような食事を常に提供しなくてはならないのである。
例えば最も基本的に思えるパスタの茹で方ひとつとっても、気を使うという。
「現地のスタッフに『僕らもパスタぐらい茹でられるよ』と言われても、僕が茹でます。だいたい失敗してのびた麺、味のない麺になっちゃうんですよ。日本人はアルデンテの美味しさを知っていますが、海外ではほとんどアルデンテにこだわっていませんから」
パスタの茹で方は教え込めばどうにかなるかもしれないが、厨房のスタッフが英語を理解しないときもある。それでも協力してもらわなければ、仕事がまわらない。そんな時、西は身振り手振りで必死にコミュニケーションを取りながら調理をしているのだ。
食材の調達も仕事の一つ。飛行機に持ち込める量には制限があるので、魚、納豆など十分な量を現地で仕入れるのが難しいもの以外は、基本的に現地で確保する。現地のスーパーや市場で米やパスタ、肉などを買い付けることも多い。欧米の先進国であればクオリティに心配はないが、発展途上国では日本と同じレベルのものを確保するのは簡単ではない。
こういう環境だから気苦労は絶えないのだが、そんな状況下でも西は栄養面の充実だけでなく、いかに選手に美味しい料理を提供し、満足してもらうかを考えて続けてきた。
「食事には、選手のストレスを軽減させたり、ホッとするような時間を作る役目があると思っています。例えば南アフリカワールドカップの時、選手は宿舎から外に出られなかった。そういうストレスがたまる状況で、唯一の楽しみが食事の時間です。そこでみんなに美味しい料理を出せば、会話も弾む。ただ栄養つけるだけの空間じゃなくて、人と人の心の通う空間にもなるし、それが引き金になってもっと深まる交流があるかもしれない。食事の時間が少しでも良い成績を残せるようなひとつのパーツになればと思っています」
この想いを形にするために、西はふたつのアイデアを実行した。ひとつが就任当初から始めたライブクッキング。西が食堂で調理をして、できたての料理を選手に提供している。
「ビュッフェで2時間前に作った料理が、固くなったり伸びたりしていたら、誰も食べたくないじゃないですか。僕が就任する前は代表もその状態だったから、みんな食べずに残っていました。でも、目の前で作ったアルデンテのパスタ、焼き立ての肉なら食べたくなりますよね。今は、パスタとステーキがメインですが、オムレツも、パプリカは入れないでとか、そういうひとりひとりのリクエストを聞いて作っています」
できあいの食事と、目の前で調理してもらいながら焼き加減や味付けを注文できる食事では、満足度に雲泥の差がある。これは選手に大好評で、行列ができるだという。
もうひとつは、「なごみのメニュー」と「サプライズメニュー」。これは、ラーメンやお好み焼きなど遠征先ではなかなか食べられないようなメニューを出すことで、選手やスタッフの気持ちを食事で盛り上げるためのものだ。
04年、中国で行われたアジアカップではカエルを食材として使用したことがあるそうだが、その裏にはこんなエピソードがあった。
「日本バッシングがあった時期でしたが、重慶の雰囲気は普通だったので、街に出て買い物をしたりしていました。それである時、小笠原さんと市場に行ったら『(食事に)カエルを出そう』と言い出したんです。小笠原さんはちょっとやんちゃなところあるんですよね。それで『え、大丈夫? 味は鳥と似てるけど』と答えたら、『じゃあ、鳥だって言って出そう。食べた後に言えばいいよ』って(笑)。それでカエルを仕入れてから揚げにして出しました。もちろん、ちゃんとカエルと伝えて出しましたけど、意外に好評でしたよ」
南アフリカワールドカップの時には、現地で仕入れた牛タンを出したら、おかわりをする選手が続出したそうだ。
食事を通していかにチームに貢献できるかを意識している西にとって、「なごみのメニュー」と「サプライズメニュー」は、張りつめている選手の緊張を解放するひとつの手段。それだけにいろいろと考えて準備するのだが、時には残念な結果に終わることもある。
「以前、茶そばを出したんです。普段、昼間はパスタだけなんですけど、たまにはいいかなと思って。そしたら中村(憲剛)さんがすぐに『茶そばって初めてですよね、遠征で!』と言ってくれました。中村さんの反応を見て、これはみんな食べてくれるなと思ったんですが、結局、食べてくれたのは中村さんだけ。しょうがないから、スタッフの皆さんに食べてもらいました。下茹でして、一人分ずつ玉を用意して、また温めて、けっこう準備が大変だったんですけどね……」
こういう時、ただ単にうなだれるのではなく、課題を探すのが西だ。
「茶そばを出すタイミングが早かった。日本食が恋しくなってから出したほうが良かったかもしれない」
こうしていつも試行錯誤しながら、選手やスタッフを喜ばせようと思案しているのだ。
決勝トーナメント進出を決めた時の歓喜の様子が
大きなパネルで店頭に飾られている
数多くのサッカー関係者やファンが訪れる
食堂でライブクッキングをしていることもあり、西はいつも食事の様子を見ている。ジーコ、イビチャ・オシム、岡田武史、ザッケローニという4人の監督も、食事の時間はそれぞれの特徴があったという。
「ジーコは、食事の時は仕事の話はせずに食事を楽しもうという感じで、笑い声が絶えないテーブルでした。オシムの場合、ご飯を食べられるだけで幸せだと思わなきゃいけないという厳格な雰囲気。ただ、食事終わってワインを飲むと楽しそうでしたね。岡田さんは、ワールドカップまではマスコミに叩かれていたから、緊張感があって一言もしゃべらないし、周りのスタッフもびりびりしていました。ただ、ワールドカップが始まって勝った後は笑顔になって、ぜんぜん雰囲気が変わりましたよ。ザッケローニは陽気ですけど、ジーコほどじゃありません(笑)」
4人のキャラクターを考えると、なんとなく想像がつくだろう。やはりラテン系2人は陽気でオシムは哲学的、岡田監督の様子からは極度の重圧とその解放が伝わってくる。
食事は基本的にリラックスする時間だが、試合前には雰囲気が一変する。西はその様子を「スイッチが入った感じ」と表す。
「ほとんどの人が緊張感に包まれているし、自分の世界に入っている。お昼頃の試合であれば、前日の夕食から戦闘モードです。試合前日の夕食までは僕も選手と笑って話したりするけど、当日は絶対に許されないことです」
試合当日、西は選手たちを見送り、ホテルのテレビで試合を観る。試合を終えて戻ってきた選手は栄養補給のためにすぐに食事をするので、その用意をしなくてはならない。
ただ、ホテルと試合会場が近かったり、特別な試合の時はスタジアムに行き、選手と監督のベンチの後ろに用意されているスタッフ用のベンチで観戦することもある。
例えば、南アフリカワールドカップのデンマーク戦では、日本代表が決勝トーナメント進出を決めた瞬間を現場で味わった。
選手たちとハイタッチをかわし、抱き合って勝利を祝う。それは、06年のドイツワールドカップの惨敗を経験し、オシムの後を継いだ岡田監督の苦悩、直前までなかなか結果を出せなかった選手たちのプレッシャーを肌で感じていた西にとっても特別な瞬間だった。
決勝トーナメント1回戦のパラグアイ戦に敗れて岡田ジャパンの快進撃は幕を閉じたが、南アフリカワールドカップ後も、代表専属シェフとしての仕事は続いた。11年のアジアカップ優勝の瞬間にも立ち会い、日本代表の一員としてブラジルワールドカップに向けて大きな手ごたえを感じていた。
しかしその1ヵ月半後、西の人生を大きく揺るがす“事象”が起きた。
東日本大震災と福島の原発事故だ。
サッカー日本代表専属料理人、最後の挑戦 厨房で闘うワールドカップ [後編] に続く
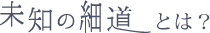
- ドラぷらの新コンテンツ「未知の細道」は、旅を愛するライター達がそれぞれ独自の観点から選んだ日本の魅力的なスポットを訪ね、見て、聞いて、体験する旅のレポートです。
テーマは「名人」「伝説」「祭」「挑戦者」の4つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、気になる祭に参加して、その様子をお伝えします。
未知なる道をおっかなびっくり突き進み、その先で覗き込んだ文化と土地と、その土地に住む人々の日常とは――。
(毎月2回、10日・20日頃更新予定) 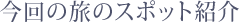
-
-
update | 2014.6.20
サッカー日本代表専属料理人、最後の挑戦 厨房で闘うワールドカップ [前編]
- 広野町レストラン アルパインローズ
- サッカー日本代表の専属料理人である西芳照さんがシェフを務めるレストラン。
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字二ツ沼46-1
Tel&Fax:0240-27-1110
Web:アルパインローズ ※Jヴィレッジレストラン ハーフタイムの情報もこちら
営業時間:
昼 11:30~13:30(L.O. 13:00)
夜 18:00~22:30(お料理L.O. 21:30 / ドリンクL.O. 22:00)
※金土日祝はランチのみ
定休日:月曜日
- Jヴィレッジレストラン ハーフタイム
- Jヴィレッジは震災以降、原発事故収束のための中継基地となっているが、ランチタイムは一般の方も利用できる。
〒979-0513 福島県双葉郡楢葉町山田岡美シ森8 JFAナショナルトレーニングセンター Jヴィレッジ内
営業時間:
月~金 11:00~14:00(L.O. 13:30)
土日祝 11:00~13:30(L.O. 13:00) - JFAナショナルトレーニングセンター Jヴィレッジ
- サッカー日本代表も利用する本格的な屋内トレーニング設備を備えたフィットネスクラブがある。
〒979-0513 福島県双葉郡楢葉町山田岡美シ森8
Tel:0240-26-0111
Web:Jヴィレッジ

ライター 川内イオ
1979年生まれ、千葉県出身。広告代理店勤務を経て2003年よりフリーライターに。
スポーツノンフィクション誌の企画で2006年1月より5ヵ月間、豪州、中南米、欧州の9カ国を周り、世界のサッカーシーンをレポート。
ドイツW杯取材を経て、2006年9月にバルセロナに移住した。移住後はスペインサッカーを中心に取材し各種媒体に寄稿。
2010年夏に完全帰国し、デジタルサッカー誌編集部、ビジネス誌編集部を経て、現在フリーランスのエディター&ライターとして、スポーツ、旅、ビジネスの分野で幅広く活動中。
著書に『サッカー馬鹿、海を渡る~リーガエスパニョーラで働く日本人』(水曜社)。
![サッカー日本代表専属料理人、最後の挑戦 厨房で闘うワールドカップ [前編]](images/title.png)
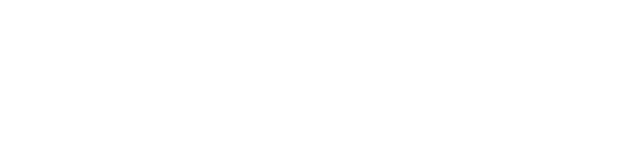
![サッカー日本代表専属料理人、最後の挑戦 厨房で闘うワールドカップ [後編]へ](images/kouhenhe.png)
