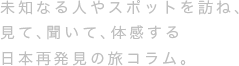#5畑仕事と箒づくり
2015年、大学院を卒業したフクシマさんは酒井さんに弟子入りした。
「弟子入りと言っても手伝いの対価として教えてもらうわけではなく、週末に教わりにいくという贅沢なものでした。『一生懸命だから教えてあげるよ』って優しく言ってくださって。平日はアルバイトをしながら夜に箒を作り、週末にそれを見てもらう。畑作業のお手伝いしながら、肥料の種類なども学びました」
ホウキモロコシの栽培と、箒づくりは交互にやってくる。春に種まきをして7月下旬から8月にかけて収穫。畑のメンテナンスをしながら翌春まで箒を作り続けるのだ。

最初の2年間は、学生時代に住んでいたアパートの大家さんが貸してくれた小さな畑で栽培を始めた。その年は冷夏だったためにアブラムシが大発生、なんとか収穫したホウキモロコシで作れた箒は5本だけだった。
そして3年目からは、700平方メートルの広い畑へ。それまで大きな畑に移りたいという思いはあったものの、土地自体は余っていても貸してくれる人と出会うのが難しかったそうだ。しかし3年目アルバイト先の人の紹介で、ようやく畑を貸してもらえることになった。
「それまではバイクのうしろに肥料をくくりつけて運んでいたんですが、3年目には軽トラックも買って。アルバイトを辞めて専業になり、いろいろ条件が揃ったタイミングでした」
-
 ホウキモロコシが並ぶ列のあいだを、こうやって草むしりする。
ホウキモロコシが並ぶ列のあいだを、こうやって草むしりする。 -
 大敵アブラムシ!
大敵アブラムシ!
-
 小柄なフクシマさんを、もうすぐ追い越してしまいそうな力強さ。
小柄なフクシマさんを、もうすぐ追い越してしまいそうな力強さ。 -
 奥までぐっとカーブしたここ全てが、フクシマさんの畑だ。
奥までぐっとカーブしたここ全てが、フクシマさんの畑だ。
畑が広くなれば、作業量ももちろん増える。フクシマさんはひとりで管理しているため、炎天下の下で何時間も草取りをしたり、雨のなかで作業する日もある。大きな畑では、効率のいい進め方やほどよい手の抜き方を学んでいった。
「たとえば最初の頃、抜いた草をそのまま置いていたら翌日の雨で根付いてしまって。雨が降るんだったら取った草はちゃんとかき集めておかないとだめだ、と学びました。でも広い畑で1年間やってみて、ひとりでもなんとかできる規模を身体で理解できたと思います」
箒づくりを実際に見せてもらうと、「言葉で説明するのが難しい」というフクシマさんの言うとおり、少し覗いたくらいでは簡単に理解できない。ホウキモロコシの縦に裂いた片方を中心でまとめて柄に縛り付け、外側の半分を糸でしっかりと編んでいくのだ。
フクシマさんが作るのは『蛤型』と呼ばれる独特の編み方。栃木県の鹿沼から引き継がれ、大正8年(1919年)に書かれた資料にも主流の形として描かれていた大穂の箒の特徴だったが、箒産業の最盛期では「東京で売れる形」や「手間がかからない形」などのバリエーションの普及により薄まっていったそうだ。
「蛤型は、手間がかかって難しいから別の作り方を選ぶ人が多くなっていったんだと思います。今でも作れるのは師匠くらいでしょうか。でも手間がかかるぶん、丈夫で絶対にバラけてこない。以前、お客さんから網目まで穂先がすり減った写真が送られてきたんですよ。そのくらい、使っているうちにバラバラと抜けてくる箒とは違うんです」
-
 蛤型は、半分に裂いた片方を中でギュッと縛って
蛤型は、半分に裂いた片方を中でギュッと縛って -
 外側の半分を糸でしっかりと編んでいく。
外側の半分を糸でしっかりと編んでいく。
1本作り上げるのに2時間弱。飾りも入れるとさらに1時間かかる。師匠の箒は形もきれいで、1時間で編み上げてしまう、とフクシマさんは言う。箒職人を目指してからまだ5年。目指すところは近いようで遠い。
「師匠には一人前になるまでに7年かかるって言われました。師匠の手は厚くて、指が太くてムッキムキなんですよ。実は私も、大学院での体験を含めれば、今年で7年目。だいぶ手が変わってきて、糸を引っ張っている左手の中指だけが伸びました」
-
 最初の頃は背中がバキバキになって起き上がれなくなるほどだったそう。
最初の頃は背中がバキバキになって起き上がれなくなるほどだったそう。 -
 自分の体重でしっかりと糸が固定されるように作った作業台。
自分の体重でしっかりと糸が固定されるように作った作業台。
未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。