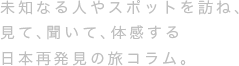#7東京漂流ライフ

高校を卒業してついた仕事は、昭和記念公園の庭師見習いだった。
「でも、わずか二日でやめたんです! 蜂に刺されてアナフィラキシーショック(短時間のうちに起こる激烈なアレルギー反応。場合によっては生命を脅かす危険な状態になることも)が起こったんです。でも、先輩たちはそれを笑ってた。人が死ぬかもしれないというのに! それで、やめました」
次についた仕事は、「なんか面白そう」というノリで受けた大手製薬会社。入社試験はものすごい倍率だったのだが、出題された試験問題がたまたま大好きなNK細胞に関するもので、見事に突破を果たす。研究開発部に配属され、その会社で初めての高卒の研究職員となった。
しかし、もともと研究者でもない彼には、何の仕事も与えられず、上司には「あなたは使えない。給料泥棒ね」と嫌味を言われるようになる。
「それは、辛かったですねえ」と私は相槌を打った。しかし、彼はあっけらかんとしている。
「いやあ、全然辛くなかったです! ずっと釣りの本とか読んでましたから。でも、この『座っている世界』ってやっぱりイヤだなあと思って。手に職をつけようと思いました」
そこから、いろいろな職業を渡り歩く東京漂流ライフが始まった。
八百屋、ラーメン屋、ガードマン…….とにかく、嫌いなデスクワークを避けながら、鮎釣りに精を出す日々。そして、24歳で一年発起して調理師の免許を取得。蕎麦にはまり、一流の蕎麦屋で修行を始めたが、そこはミスをしたらフライパンが飛んでくるという戦場のような職場環境。じわじわと窒息するように体力と気力が奪われ、ある夜、上司とけんかになり蕎麦屋を去ることを決意した。
その後はテレビ局の人に声をかけられ、閉園直前のムツゴロウ王国で動物の面倒をみていたこともあった。
「もう疲れ果てました。あの頃は、何にもやる気がしなかった」と土屋さんは言う。
大都会で流されていく日々。そして、まだ何者にもなっていない自分。これからどこでどうやって生きていったらいいのだろうか。答えは出なかった。
そして、半ば鬱状態に陥った彼は、高校時代の経験をなぞるように、再び故郷の森に戻ってきたのだった。
「最初は山に入って、ただじっと座っているだけでした」
木々のざわめきに耳を澄ます。雲の流れを見つめる。川の冷たい水に触れる。
ぼうっとしているうちに一週間が経過した。そのうち、少しずつエネルギーが体に満ちてくるのを感じた。
「そうだ、人間には森が必要なんだ。僕たちは自然に生かされているんだと強く感じました。やっぱり僕は森と一緒に生きようと決めました」
その時、十数年続いた漂流ライフは終わりを告げた。そして栃木でのネイチャーガイドやアウトドアクッキングの経験を経て、再び彼は故郷の森に戻ってきた。
未知の細道 No.55
最新の記事
- 物でも思い出でもない、新しい旅のおみやげに出会う旅「生きる術」を持ち帰る離島の農家民宿へ2019.1.25
- 職業欄は冒険家!?山形の大自然が生んだ冒険家・大場満郎さんの「死ぬまで輝いた目で生きる」という人生の挑戦2019.1.10
- 「相撲が好きじゃけん」日本で一番相撲を愛する町で167年続く伝統の相撲大会 乙亥(おとい)大相撲を愛媛へ見に行く2018.12.25
同じライターの他の記事
- 美咲芸術世界が織りなすヘンテコな世界〜パリから棚田に舞い降りた常識ハズレの風雲児たち〜2018.9.10
- 高円寺に出現した謎の巨大壁画を探せ!街の“予定調和”を崩すアート2018.8.10
- わたしたちは誰もが芸術家なのか?「黒板消し」から始まった小さな美術館がいま伝えたいこと「カスヤの森現代美術館」2018.5.10
人気の記事
- 寿町は「危険な街」なのか? 寿・黙示録2016.10.10
- 100時間、絶食したことはありますか? 世にもストイックすぎる成田山新勝寺の断食修行に挑戦! 2016.5.25
- 究極の苦行で時を超えた偉人を訪ねて あなたは即身仏を知っていますか?2017.11.25

川内 有緒
コンサルティング会社やシンクタンクに勤務し、中南米社会の研究にいそしむ。その合間に南米やアジアの少数民族や辺境の地への旅の記録を、雑誌や機内誌に発表。2004年からフランス・パリの国際機関に5年半勤務したあと、フリーランスに。現在は東京を拠点に、おもしろいモノや人を探して旅を続ける。書籍、コラムやルポを書くかたわら、イベントの企画やアートスペース「山小屋」も運営。著書に、パリで働く日本人の人生を追ったノンフィクション、『パリでメシを食う。』『バウルを探して〜地球の片隅に伝わる秘密の歌〜』(幻冬舎)がある。「空をゆく巨人」で第16回開高健ノンフィクション賞受賞。
未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。