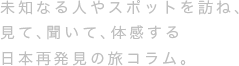#10月のリズムで生きる豆腐屋さん

さて、いよいよ最後の目的地、「月のとうふ」へ。
商店街をゆっくり進む。豆腐屋さん、豆腐屋さん…….っと。そういえば、最後にお豆腐屋さんに行ったのはいつだろうと考えたが、もう覚えていなかった。
ガラガラと引き戸を開け、「こんにちは」と声をかけたが、誰もいない。何気なくショーケースを覗く。がーん! なんと空っぽだ。
ここの豆腐は大人気で、夕方にはすべて売り切れると聞いていたが、噂通りであった。
店主の周浦宏幸さんは、「あ、すみませんねえ!」と、のんびりとした口調で奥の厨房から現れた。

ここの開店は2009年。周浦さんも移住者、つまりは「外から来た菌」であった。
東京でサラリーマンをしていて忙しい生活に疲れ、豆腐屋になることを決意し、東京のお豆腐屋さんで修行する。そこが神崎の大豆を使っていて、とてもおいしかった。
それと同時に神崎にはお豆腐屋さんが一軒もないというパラドックス的な状況を知る。そこで周浦さんは、神崎の大豆で豆腐を作り「Little Forest ゆうゆう」などで販売してみた。すると徐々に人気が出て、やがて二百丁を完売する人気商品になった。神崎の人が、神崎の大豆の美味しさを再発見したのだ。
そのことに背中を押され、2009年に河岸通り商店街に夫婦で「月のとうふ」を出店。この商店街では実に35年ぶりの新規の店である。使うのは地大豆と地下水、にがりだけで、絹、木綿などの新鮮な豆腐を毎日作る。その他にも油揚げ、がんもなどの揚げ物、そして日によっては、満月どうふ(ざる豆腐)、朧月(カップに入った柔らかい豆腐)などのちょっぴりオリジナルな豆腐も。
ところで、「月のとうふ」というユニークな店名は、どこからきたのだろう。
「抽象的なんですけど、サラリーマン生活というものが太陽が(世の中)を支配する太陽歴で動いているとしたら、豆腐屋としての生活は、月の満ち欠けなんかを感じながら、月のリズムで過ごしていきたいというような漠然とした想いがあって。自然と一体となってやりたいなと」
そんな想いでゆったりと作られた豆腐だから、きっと誰が食べてもおいしいのだろう。優さんや福士さんが口を揃えて言う通り、そういう想いはきっと微生物に届いているに違いない。
未知の細道 No.64
最新の記事
- 物でも思い出でもない、新しい旅のおみやげに出会う旅「生きる術」を持ち帰る離島の農家民宿へ2019.1.25
- 職業欄は冒険家!?山形の大自然が生んだ冒険家・大場満郎さんの「死ぬまで輝いた目で生きる」という人生の挑戦2019.1.10
- 「相撲が好きじゃけん」日本で一番相撲を愛する町で167年続く伝統の相撲大会 乙亥(おとい)大相撲を愛媛へ見に行く2018.12.25
同じライターの他の記事
- 美咲芸術世界が織りなすヘンテコな世界〜パリから棚田に舞い降りた常識ハズレの風雲児たち〜2018.9.10
- 高円寺に出現した謎の巨大壁画を探せ!街の“予定調和”を崩すアート2018.8.10
- わたしたちは誰もが芸術家なのか?「黒板消し」から始まった小さな美術館がいま伝えたいこと「カスヤの森現代美術館」2018.5.10
人気の記事
- 寿町は「危険な街」なのか? 寿・黙示録2016.10.10
- 100時間、絶食したことはありますか? 世にもストイックすぎる成田山新勝寺の断食修行に挑戦! 2016.5.25
- 究極の苦行で時を超えた偉人を訪ねて あなたは即身仏を知っていますか?2017.11.25

川内 有緒
コンサルティング会社やシンクタンクに勤務し、中南米社会の研究にいそしむ。その合間に南米やアジアの少数民族や辺境の地への旅の記録を、雑誌や機内誌に発表。2004年からフランス・パリの国際機関に5年半勤務したあと、フリーランスに。現在は東京を拠点に、おもしろいモノや人を探して旅を続ける。書籍、コラムやルポを書くかたわら、イベントの企画やアートスペース「山小屋」も運営。著書に、パリで働く日本人の人生を追ったノンフィクション、『パリでメシを食う。』『バウルを探して〜地球の片隅に伝わる秘密の歌〜』(幻冬舎)がある。「空をゆく巨人」で第16回開高健ノンフィクション賞受賞。
未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。