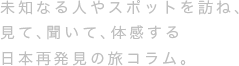#4発酵とは、元気になること

「どうぞ、こちらは釜屋ですよ」と案内された部屋では、巨大な釜で豆が煮えていた。蓋をあげるとふわあっと湯気が上がり、すばらしい豆の香りが立ち込める。釜の下では、薪の火が勢いよく燃えていた。薪の釜は今や全国的にも珍しい。手間暇はかかるが、ふっくらと大豆や米を炊き上げてくれるそうだ。それらが味噌や糀の材料となる。

「はい、こっちが“むろ”(糀室)ですよ!」
次は天井が低く、蒸し暑い部屋に案内された。この部屋で蒸米に糀菌を入れて寝かせ、ゆっくりと四日をかけて発酵させる。もわっと湯気が立ちこめ、サウナみたい。たしかに、こりゃあ、菌がよく育ちそうだ。
ここでは、私たちが普段は忌み嫌っているカビや菌こそが大事な主役だ。微生物たちが活躍し、米の有機物を分解し、美味しいものに変化させる、それこそが発酵なのだ。ふむふむ。
ちなみに糀菌は、「国菌(こっきん)」(初めて聞いた!)。つまり、日本にしか存在しない独自の菌のこと。これがなかったら、お味噌は存在しない。おお ありがたや。


そして、発酵が終わると、最初に見た白い綿菓子のような状態になる。これと、炊いた豆、塩を混ぜて寝かせれば、味噌になるというわけだ。
「この人(仁さん)は、この白い“糀の花”を咲かせることにこだわってるんですよ!」
と照れ屋な仁さんにかわって、資子さんが説明してくれる。
発酵の状態をきちんと見極め、“糀の花”を咲かせるのは簡単ではない。仁さんは、夜中に何度も起きて蒸米の変化を観察し、糀箱の場所を入れ替えたり、温度を変えたりして、糀菌たちの働きを手助けする。そして見事に花が咲いたら出荷となる。しかし最近は、“花”を見たことがない人も多いらしく、カビが生えていると驚いて、「食べられるんですか」と問い合わせてくることもあるのだ、と資子さんは笑う。
それでも、空前の発酵ブームのおかげか、今や手作り味噌を作る人は増えていて、糀屋さんも大忙し。そうやって、発酵食品に再び光が当たることを、資子さんはとても喜んでいる。
「発酵って、元気になること。食べた人も元気になるし、買っていただけて、作り手も元気になります! ほら、これで甘酒でも作ってみてくださいね。簡単ですよ」と資さんは私に糀とお味噌や甘酒のレシピをもたせてくれた。
確かに、あのご夫婦は元気そうだなもんなあ! なんて考えながら、私は、ずっしりとした糀の袋を手に下げて次なる目的地に向かった。