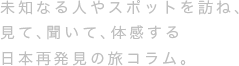#4映画監督になるまで

現在、33歳の鈴木さんは茨城県日立市の生まれ。日立製作所に勤めながら市民劇団に入っている演劇好きな両親と、子どもの頃から東京の美術館に連れて行ってくれる祖父母に囲まれて育った。
映画も小さな頃からよく見た。最初に映画を見始めた記憶は3歳の頃、しかも『2001年宇宙の旅』(スタンリー・キューブリック)を冒頭のシーンと最後のシーンを、毎日繰り返し鑑賞していたという。「小学1年生から高校にあがるまでずっと絵も習わせてもらったし、アートの世界に進もうと思うには何の障害もない、その意味では恵まれた家庭だったと思います」
でも高校生1年生になった時、鈴木さんは絵を習うのをやめた。習っていた絵画より映画の方が自分に合っている、実験映画を作りたい! と思うようになっていた。そして多摩美術大学に当時あった映像演劇科に入り、ここからは、とにかく映画を作ることだけに邁進するのである。
大学では実験映画で有名な、ほしのあきらさんの授業に大きな影響を受けた。「その授業はとにかく厳しくて。映画を作るのにまず、企画の面談があるんです。そこで先生に、こういう映画を撮りたい、とプレゼンするんだけど、初めての面談で、お前の言ってることは全然つまらないんだよ! とひどく怒られました」
その時、鈴木さんは、映画を撮るのに技術は関係なくて、どれだけ自分のプロジェクトに切実に立ち会えるのか? それを先生は問うているんだ、と気づいたのだという。
それからはずっと「自分と対象との距離を、どれだけ突き詰められるか? ということを考えて映画を作ってきました。それがきちんとできれば、テクニック的なこと、例えば適切な画角も自然と決まっていくんです」という鈴木さん。ほしのさんもそれ以後は「お前はそれでいい」と言って、ずっと自由に映画を作らせてくれた。

大学では映画を通して共感できる人たちに出会うことができた。しかし卒業してからは、映画作りもなかなかうまくいかなかった。東京でその日暮らしのような仕事もしてきたが、このままじゃダメだと思い、2009年に故郷の日立に帰った。それがまた新しい転機につながる。
日立に帰ってから、両親が関わっていた演劇のコミュニティに顔を出すようになった。地元で映画を作るための仲間が欲しかったからだ。
ここで鈴木さんは、誰よりも熱心に映画作りを手伝ってくれるひとりの女性に出会う。その人は今、鈴木さんの奥さんになった。そして奥さんの出身地である水戸に移り、二人の子どもにも恵まれた。
「東京だったら結婚して子どもを持って、映画を作るなんて無理でしたねえ」と鈴木さんは言う。
そうして鈴木さんは2012年に「シアネスト・オーガニゼーション大阪」という、映画制作の活性化を図る組織から助成を得て、自身初の長編映画『丸』を作るのである。それは実は2011年に故郷で経験した、東日本大震災と決して無関係ではなかった。
未知の細道 No.109
最新の記事
- 物でも思い出でもない、新しい旅のおみやげに出会う旅「生きる術」を持ち帰る離島の農家民宿へ2019.1.25
- 職業欄は冒険家!?山形の大自然が生んだ冒険家・大場満郎さんの「死ぬまで輝いた目で生きる」という人生の挑戦2019.1.10
- 「相撲が好きじゃけん」日本で一番相撲を愛する町で167年続く伝統の相撲大会 乙亥(おとい)大相撲を愛媛へ見に行く2018.12.25
同じライターの他の記事
- めざせ!日本一のサイクリングの街・土浦 路地裏から湖までを巡る自転車の旅2018.10.10
- 今も昔も女の子をときめかせる美しき雛人形「桂雛」の世界2018.9.25
- 77万年前の地磁気逆転地層を目指して!養老川と地層を巡る2018.7.10
人気の記事
- 寿町は「危険な街」なのか? 寿・黙示録2016.10.10
- 100時間、絶食したことはありますか? 世にもストイックすぎる成田山新勝寺の断食修行に挑戦! 2016.5.25
- 究極の苦行で時を超えた偉人を訪ねて あなたは即身仏を知っていますか?2017.11.25

松本美枝子
主な受賞に第15回「写真ひとつぼ展」入選、第6回「新風舎・平間至写真賞大賞」受賞。
主な展覧会に、2006年「クリテリオム68 松本美枝子」(水戸芸術館)、2009年「手で創る 森英恵と若いアーティストたち」(表参道ハナヱ・モリビル)、2010年「ヨコハマフォトフェスティバル」(横浜赤レンガ倉庫)、2013年「影像2013」(世田谷美術館市民ギャラリー)、2014年中房総国際芸術祭「いちはら×アートミックス」(千葉県)、「原点を、永遠に。」(東京都写真美術館)など。
最新刊に鳥取藝住祭2014公式写真集『船と船の間を歩く』(鳥取県)、その他主な書籍に写真詩集『生きる』(共著・谷川俊太郎、ナナロク社)、写真集『生あたたかい言葉で』(新風舎)がある。
パブリックコレクション:清里フォトアートミュージアム
作家ウェブサイト:www.miekomatsumoto.com
未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。