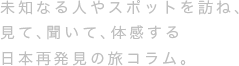『旅の思い出』編 「地域のアートセンター」発 美学を学ぶ仲間と論文の世界へ、旅をする
写真= 山野井咲里(表記のないものすべて)・松本美枝子ほか
未知の細道 No.170 |25 September 2020
#5常陸太田の片隅から、75年前のヨーロッパを想像する

短い論文をまず一つ読み終えた私たちは、舘さんの発案で、次にフランスの哲学者であり美術家の、ジョルジュ・ディディ=ユベルマンの論文『イメージ、それでもなお アウシュビッツからもぎ取られた4枚の写真」(平凡社)を読むことになった。
これは、第二次世界大戦末期のナチスの強制収容所のなかで、囚われたユダヤ人達が必死の抵抗を試みて、ガス室での大量虐殺の前後の状況を秘密裏に撮影した写真についての論文だ。
想像を絶する地獄の絶滅収容所で、死ぬ運命にあることを自ら知っていたユダヤ人達。自分たちの置かれた状況、そしてナチスの非道な行いを、なんとかして外の世界に伝えようと、外部のレジスタンスの力を借りてカメラを入手し、ようやっと撮られた写真が4枚だけ現存している。ナチス側が撮った強制収容所の記録写真は大量に残されてはいるのだが、それらとは明らかに一線を画す、不鮮明なこの4枚の写真は、2020年現在でもなお、ユダヤ人収容者達が撮った「唯一」の写真として位置付けられている。
「唯一」の存在であるからこそ、この写真については、戦後のヨーロッパで様々な論議が交わされてきた。戦後のヨーロッパは、政治も文化もすべて、この戦争の傷跡を知り、学び、批判し、反省することからはじまっている。特に美学の世界において、この特別な4枚の写真の取り扱い方が、ときには批判の対象となることもあった。
それはつまりこういうことである。ナチスのユダヤ人絶滅政策はこれまでの人類には想像不可能な行いであって、いくつかの写真で代表することなど到底できない。「イメージが限定されてしまうような写真よりも、地獄を生き残った人たちの証言こそが、想像不可能な事態を唯一想像出来る、真の記録だ」という主張だ。
ユベルマンの論文の骨子は、そのような批判を乗り越え、この写真が、生存者の証言と同じように資料性として意味があり、人間の〈想像力〉について可能性をもたらす存在になりうる、とする。なぜならこの4枚の写真は単なるイメージではなく、希望なき撮影者が、「それでもなお」この写真がどこかへ届くはずだと信じて、外の世界へと希望を託したものだからだ。
これは写真の可能性を考える上で重要な文献なのだ、と舘さんは言った。そしてこの本を読みながら、写真や想像力について考えてみよう、と提案してくれたのだった。
だが読み始めてみると、この論文は思った以上に難しかった。強制収容所のガス室を経験した人は誰も生き残っていないし、その直接の記録は一つも残っていない。ただその前後の状況の写真があるだけだ。〈記録がなく、本質的には想像しようがない事実を、それでもなお想像すること〉が、まず途方もなく難しいのだ、ということが、この論文を読めば読むほど、よくわかったのだった。
しかしそれを乗り越えていかなければ、写真の存在や、想像できないことを記録する行為自体が、無意味なものとなりかねない。私たちはこの論文の命題を少しでも理解するために、哲学、歴史、映画などさまざまな関連資料を学ぶようになった。
そうして4人で勉強を進めていくうちに「戦前のユダヤ人やドイツ人のコミュニティの歴史を、日本のなかで、いちばん感じとることができる地域は神戸だね」という話をするようになった。戦前から外国に開かれていた港町・神戸には今も異人館街が残っており、かつてそこにはドイツなどヨーロッパ各国の商館やクラブがあった。そのようなコミュニティには、戦前戦中、ドイツ高官も出入りしていた、とも言われている。また神戸はナチスの迫害から脱出し、自由の国へ亡命しようとするユダヤ人たちが、最初に経由した場所のひとつでもあった。現在でも日本に二カ所しかない、ユダヤ教会のひとつが神戸にはあるという。
そして神戸は、なんといっても聡子さんが生まれ育ち、舘さんが写真論を学んだ街でもある。その神戸に行って「4人で史跡を見てみたいね」という話が持ち上がった。論文に書かれている歴史に、わずかではあるがリンクしている、実際の場所をこの目で視察すれば、76年前の状況も、もう少し「想像」できるかもしれない。

未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。