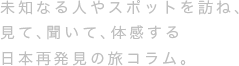日本一の芋煮会フェスティバルの知られざる舞台裏 6.5メートルの大鍋がつなぐ輪
写真= ロマーノ尚美(表記があるもの以外すべて)
未知の細道 No.292 |10 November 2025
#7空を見上げて青年部の夢は続く
大鍋の芋煮がお腹のなかで消化したころ、3メートル鍋で作られる「しお芋煮」のゾーンへ向かった。
初めて食べるしお芋煮は、 醤油味に慣れた舌には少し不思議な味。でも、あっさりしていて食べやすい。隣でお椀を持っていた地元出身の男性に声をかけると、「しお芋煮は僕も初めて。でも、軍配はいつもの醤油芋煮かな」と返ってきた。

山形県の日本海側にある庄内地方や、お隣の県の仙台や福島に行くと、豚肉に味噌味の芋煮が主流らしい。そういえば、一緒に鍋太郎の設置を隣で見ていた地元の人と話をしたとき、「あれは芋煮じゃなくて豚汁よね~!」と笑っていたっけ。

芋煮でこれだけ会話が弾む。知らない人と繋がる。たった一言、二言のやり取りが嬉しいのは、私も山形を、芋煮を愛しているからだろう。
午後3時、鍋太郎のお腹に抱かれた3万食の芋煮は完売して、今年のフェスティバルは幕を閉じた。
夕暮れに車で双月橋に向かうと、河川敷ではすでに撤収が終わろうとしていた。SNSを見ると、足場から「ご苦労さん」と降ろされるバックホーや、再びクレーンでかまどから降ろされた鍋太郎が洗浄されている様子がアップされていた。これほどの規模の会場が、なにもなかったように片づけられていく。そこにいるのは、やっぱり空色のTシャツ姿の人たちだった。

「ファーストフード店では"スマイル0円"といいますけど、芋煮会フェスティバルは"ガッツ0円"ですよね」
取材の時にそう言うと、五十嵐さんは笑いながらうなずいた。
「実行委員会にもボランティアにも、人件費というカテゴリーはないですからね」

実は、五十嵐さんには"もうひとつの夢"があった。
それは、フェスティバルの空にブルーインパルスを飛ばすこと。
彼は今年の4月に委員長に就任したときに、航空幕僚長宛に手紙を出したそうだ。
「フルーツ王国・山形の150周年と芋煮会フェスティバルを記念して、って書いたんですけど、結局、叶いませんでしたね」 と照れくさそうに笑う。
「最初は"やれ"って言われてテンション低く動いていた僕が、本部長をやって、委員長もやれた。もう、やりきりました。きっとまた、来年のリーダーが新しい夢を見つけてくれるはずです」
そう語る五十嵐さんの表情は、晴れやかだった。
「今度は、"やれば楽しい"を伝えるのが、自分たちの役目ですね」
富塚さんは「山形の酒蔵が"吟醸を世界の言葉に"というスローガンを出しているのがいいなと思っていて。"芋煮を世界の言葉に"って良くないですか」と、新しい発想に目を輝かせる。
実は以前、ドイツの山形県人会から"ヨーロッパで芋煮会を"という誘いもあったという。
日本一の芋煮会フェスティバルは、 芋煮を通して山形の魅力を発信する場所。
「少子高齢化で山形に若者がどんどん少なくなる。このイベントを続けるには、担い手を増やさないと」と五十嵐さんは語る。
けれど、「山形を好きだ」という想いと、ぶれない目標がある限り、青年部の「やろうぜ!」から、楽しいことがどんどん生まれていくんだろう。
数年後、フェスティバルの空を本当にブルーインパルスが飛ぶ日が来るかもしれない。
大鍋がヘリコプターにぶら下がって空を飛んだあの日からずっと、芋煮会を通して、青年部の夢は空の向こうへと続いている。

未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。