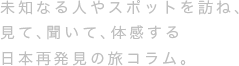#3継がないと決めていたパン屋

家の前は駐車場になっており、その一角に建てられているのがSilkroad Bakery SHERの店舗だ。青い壁の小さな小屋は、大通りを通る人たちの目にもよく止まる。
そのすぐ裏手に「タンディール」と呼ばれる窯がある。インド料理店などでナンを焼くのと同じもので、筒状になっている窯の内側にパンを貼り付けて焼いていく。外での取材に慌てて、上着を取りに戻る私。
「今日は寒いけど、夏より楽です。僕ね、腕の毛がないんですよ。焼けてつるつるになっちゃった」
羊肉と玉ねぎをパン生地で包んだサムサを、素手でペタペタと貼り付けながらシェルさんが言う。300度にもなる窯の中を覗かせてもらったら、熱風で息ができなかった。ここに手を入れるなんて、想像しただけでこわい。

サムサをすべて貼り付け終わったら、蓋をして焼けるのを待つ。イーストを入れていないパン生地は、ふんわりせずにカリッと香ばしい焼き上がりになる。
「サムサを作り始めたばかりの頃、窯を開けてみたら生地だけが残っていて、中身の肉が全部下に落ちちゃってたことがありました。生地が柔らかすぎたんだと思います」

実は、シェルさんはノンを作るパン屋の3代目。ノンの作り方は知っていたが、サムサを初めてちゃんと作ったのは日本に来てからだそう。
「キルギスにいた頃は、パン屋は絶対に継がないって決めてました。毎日朝早くから、みんなが休みの日こそ働かなきゃいけない。そんな大変そうな父の姿を見ていたので。でも父に『継がなくてもいいから、覚えておきなよ』って言われて、作り方は教えてもらってたんです」
教えてもらっていたパン作りが役立ったのは、香織さんとの結婚を機に来日したときだった。日本語がほとんどわからなくても、パン作りの知識と技術ならある。その技術があったから、多くのメディアで取り上げられる名店、ビゴ東京(BIGOT TOKYO)に採用されたのだ。
「店長も、フランス語がわからないのにフランスで働いた経験があったらしくて『大事なのは言葉じゃなくて、技術だから』って拾ってくれました」
その後、キルギスに戻ることもありながら、日本にいるときはベッカライ徳多朗などの有名なパン屋で働き、日本のパン作りとともに日本語を学んでいった。

未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。