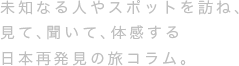#3全ては「もったいない」から始まった
「いつだれ」の原点は、そう、とし江さんの「もったいない」である。
「私は新潟のすごい豪雪地帯で生まれました。時代は、昭和の真っただ中。あの頃の田舎では、家同士の垣根が低くて、寄ってけ、食ってけ、飲んでけ! という感じだったんですね。その一方で、冬場は野菜を確保するのは大変で、漬物にしたりして凌いでいました」
そんなとし江さんが、結婚していわきに暮らすようになって約40年。近隣に広がる広大な田畑を見ていつも感じていたことがある。
「こちらでは、ご先祖様の畑を守るために食べきれないほどの野菜を作っている人もたくさんいます。それで、今ぐらいの時期になると大根なんかが、収穫されないまま花が咲いちゃってたりして、ああ、もったいないなあって! あれを料理したら食べてくれる人がいるんじゃないかなあ」
実は、同じように感じていた人は他にもいた。
とし江さんと一緒に、「いつだれ kitchen(キッチン)」の立ち上げに尽力してきた市役所職員(地域包括ケア推進課)の猪狩僚さんだ。
「うちは子どもが4人もいるので、家庭菜園をやっている人なんかから野菜をたくさんもらうんです。その一方で、俺は福祉の部署にいるので、仕事では干し芋一本で三日間しのいでいるようなおじいちゃんに会うこともある。野菜を余らせている人もいれば、十分に食べられない人もいる。そういう食のミスマッチが起こっていました」
余った食材で料理をして、食べられる場を作れないか――。別々の立場にある二人の間で、そんな似た発想がそれぞれのなかで温められていた。
しかし、発想は発想にすぎない。
それが実際に「キッチン」という形で結実した背景には、また別の方角から迫ってきた切実なできごとがあった。

「いつだれ」の立ち上げに尽力し、ほぼ毎週「いつだれ」に通う猪狩僚さん。この日はエゴマをするのを手伝っていた。
未知の細道とは
「未知の細道」は、未知なるスポットを訪ねて、見て、聞いて、体感して毎月定期的に紹介する旅のレポートです。
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。