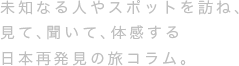#10自分ひとりじゃ社会は変えられないけれど
話を聞きながら、私はカレーにおからのサラダ、お吸い物、お餅を次々と平らげた。そのどれもが、なんでこんなにうまいんだ! と泣きたくなるくらいおいしかった。
聞けば聞くほど、ここは食堂ではなく、「キッチン」だった。食堂だと「サービスする人」と「される人」に分かれるが、ここでは誰もがキッチンに立てるし、誰もが一緒に食卓を囲むことができる。(実際に私も準備を手伝わせていただいた!)
ただ一緒に同じ釜のメシを食う。
話さなくてもいい。
食べられなければ、いるだけでいい。
ただ、一緒にいる。それだけ――。
突き詰めていけば、それが「いつだれ kitchen(キッチン)」の正体だった。
なにか誰かに食べさせてあげたい。おいしいね。ありがとう。そう思う人たちが集まれば、その場は家族のようにつながっていく。食にはそういう力があるのだ。
「とし江さんの長年の思いがここを生み出したんですねえ」
思わず私がそう言うと、彼女は「ううん、強い思いなんかじゃないの」と軽やかに首を振った。
「一人の思いが強すぎてもだめなんだと思う。私は、人が他の誰かのために何かができるなんて思ってないの。ただ自分がやりたいからやるだけ。どんな人でも、自分ひとりで社会を変えることはできない。でも、こういう場があれば、うちの玉ねぎを二個持っていこうかなって、小さな善意が少しずつ集まってくるの。それくらい気軽じゃなきゃ、こんなことできないですよ!」
そうですね、そのとおりですね。たぶん現代の日本には、「生きづらさ」を抱えていない人はほとんどいないだろう。そう思えば、この国の1億2千万人が「いつだれ」のお客さんであり、お手伝いメンバーになれそうだ。
素敵だなあ。もっと全国に広まっていけばいいなあ、なんて思うけれど、とし江さんはそれをあっさりと笑い飛ばす。
「実はあんまり先のことについて考えたことはないの。だって、もう『いつだれ』はもう動きだしちゃって、人格を持ったでしょ。あとはその流れに逆らわないで、なるようになっていくって思います。私はまたみんなとわいわい、大鍋いっぱいの田舎料理を作りたいと思っています」
気がつけば、一人、二人と手を振りながら帰途につき始めた。
「じゃあ、また来週ね!」
「うん、またきてねー」
そんな声がいち段落し、ちょっと静かになった2時すぎ。今度はお母さんたちの賄いタイムが始まった。
「じゃあ、いただきまーす!」

4月以降の営業に関しては、公式ツイッターをご確認ください。
いつだれkitchen (@itsudarekitchen) | Twitter
未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。