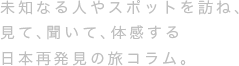大人も"子どもに戻る"場所 児童遊戯施設「コパル」で見た未来の風景
写真= ロマーノ尚美(表記があるもの以外すべて)
未知の細道 No.291 |27 October 2025
#4一人ひとりの「困りごと」に向き合う
教員としてキャリアを重ね、2011年、色部さんは市立の小学校で主幹教諭に任命された。主幹教諭とは、学校の実態に合わせて業務を担う役職。色部さんの役割は、保護者と行われる面談の統括だった。
市内でも比較的規模が大きかったこの小学校には、さまざまな”困りごと”を抱えた子どもが多く、年間かなりの数の面談が行われていた。
45分の授業に耐えられない子がいる。どう対応するか。別室で授業を受けるのか。本人にあった対応を見つけないと、本人も周りも困る。でも、保護者の了解なしには次へは進めない。不登校、いじめ、その他のトラブル。子どもと保護者と学校をつなぐ役として、色部先生の面談のファイルはどんどん分厚くなっていった。
「ひとつの学校に、これだけいろんな困りごとに悩む子どもがいるんだ」
その気づきが転機だった。それまでは「クラスの生徒」というひとつの集団として見ていた意識が、一人ひとりの面談記録と向き合ううちに変わっていく。「個々の声を聞いて、個々に応じた対応をしなければ」と。
その後、教頭として山形市内の複数の小学校に転勤したが、子どもと親のさまざまな悩みごとは絶えず色部さんの耳に届いた。担任では対応が難しいケースは、保護者から直接電話がくる。「困りごと対応」は色部先生の日常になっていった。
「一人ひとりに時間をかけるのは大変では?『そこまで構っていられない』という声は出なかったんですか」
ふと湧いた疑問をぶつけると、「それはない、ないですよ」と、色部さんは、理解できない言葉を聞いたかのように、否定を繰り返した。
「なんとかしたくてもできない子ども、どうしていいかわからない親の想いを受け止めて、『こっちに進もう』と方向を示さないと、困りごとは溜まったまま。時間があるとかないとかじゃなく、一つひとつをどう解決するか。私も他の先生たちも、常に心を砕いていました」
その言葉を聞きながら、学校で奔走する色部先生と、コパルで家族を見守る館長さんの姿が、重なった。

(画像提供:シェルターインクルーシブプレイス コパル)
未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。