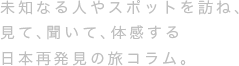大人も"子どもに戻る"場所 児童遊戯施設「コパル」で見た未来の風景
写真= ロマーノ尚美(表記があるもの以外すべて)
未知の細道 No.291 |27 October 2025
#8目の前の、一人の笑顔のために
「この先、コパルがどうなっていったらいいと思いますか?」
食堂のテーブルで、私は色部さんに尋ねた。背後から、子どもたちの明るい声が聞こえてくる。
オープンから3年目を迎えた2024年度は、来館者数が194,340人、視察件数も累計で2200件を超えたという。"コパルの輪"が確実に広がっていることを、色部さんはどう感じ、どんな未来を描いているのか。
「結局、私たちは“目の前のひとりの笑顔”を追い続けるしかないと思うんです」
色部さんはゆっくりと言葉を選んだ。「"すべての人にとって"という理想が富士山の頂上だとしたら、私たちはまだ一合目を歩いている状況です。永遠にたどり着けないかもしれないけれど、一歩一歩を確実に登っていく。コパルのインクルーシブは、そんな道のりなんです」。

耳が聞こえない人のために簡単な手話での挨拶や、タブレットを使ったコミュニケーションを取り入れ、コパルの近くにある山形県立山形聾学校の生徒の職業訓練の場にもなっている
コパルに来るまで、私は「インクルーシブ」を“仕組み”のようなものだと思っていた。段差のない通路、ユニバーサルデザインの遊具、情報の多言語化。そういった工夫の積み重ねが、インクルーシブなのだと。
でも、ここで過ごし、色部さんの話を聞いて気づいた。包み込むって、人の心の中で起こる小さな変化なのだと。誰かの笑顔にふれたとき、自分と向き合おうとする誰かの想いを感じたときに生まれる、見えない“センサー”のようなもの。それが伝播して、場全体の空気がやさしくなっていく。
「自分たちがやっているのは、気づきレベルのインクルーシブでしかない。いろいろ発信するにあたって『これって、独りよがりじゃないのかな』という迷いはありましたよ」と、色部さんは本音を漏らす。
それでも、目の前にいるひとりのために、という発想でいると、やりがいがあるし楽しい、と笑う。
「利益や評価ではなく、『ああ、今日はこの人が喜んでくれたな』と思えることが、一番の充実なんです」
その言葉を聞いたとき、すとんと腑に落ちた。コパルの空気が温かいのは、理念が立派だからじゃない。色部さん自身が、スタッフ皆がこの場所を心から愛しているからだ。好きという気持ちは、理屈を超えて伝わる。子どもたちも、その温度を敏感に感じ取っているのだろう。
「今の課題は、好きすぎて止まらなくなることですね」と色部さんは照れくさそうに笑った。
「コパルのことをわかってもらうには、いくら時間があっても足りないんです」
色部さんが「好き」全開で語るコパルの話は多くのメディアに掲載されている。その記事を読んで「先生出てたよ!」と教え子がやってきたり、同窓会で「俺行ってない、早くいかなきゃ」と色部先生とコパルの話題が出るそうだ。

(画像提供:シェルターインクルーシブプレイス コパル)
未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。