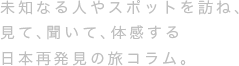町をつつむ物語 謎多き人形作家・山岡草が最後に暮らした里を歩く
写真= 松本美枝子(表記があるもの以外すべて)
未知の細道 No.287 |25 August 2025
#5芸術家の素顔

明くる日、指定の場所へと伺うと、その人は山岡との交流の日々を、少しずつ話しだした。
当時、その人は、まだ小さかった子どもと一緒に山岡の家に遊びにいくなど、親しい付き合いをしていたのだという。山岡には「あんさん、うちの人形に興味あるんかいな、見たいか〜」などと言われたそうだ。子どもたちとは工作などをしてよく遊んでくれたと言う山岡のことを、「すごく優しくて、本当に楽しい人でした」と懐かしそうに話す。

古い茅葺の家の土間にはオブジェを置き、床の間には花を生け、飛騨高山で揃えたという衝立で囲った作業場があった。庭には好んだオミナエシやシモツケソウなどをいっぱいに咲かせ、家の中も外も、芸術家らしいたたずまいだったという。

格好はいつでも作務衣と手ぬぐい巻き。山岡が家にご飯を食べくることもよくあったそうだ。スーパーに行くときは「うちこんなかっこうで、一緒に行ってもええか? ほんまに大丈夫やろうか?」と言いながら、一緒に買い物をしたという。
その人だけではない。Kさんも若かりし頃に、アルバイトで山岡の家まで集金に行ったことがあったそうだ。山岡に「あんさん、お茶飲んでいきや〜」と言われ、そのままお茶をご馳走になった。その後、就職してからも一度、職場にやってきた山岡に、「あんさん、がんばりや」とあたたかく声をかけられたことがあったのだという。「あのときの声は今も印象に残っているんです」。
人形を作っているところは誰にも見せなかった山岡だが、人形を撮影するために一輪車にすべての道具を乗せてよく野山に出かけていたという。「うちは人形とこんなことして、遊んでいるんやで」と山岡はいっていた。

山岡にとって人形は我が子そのものだったという。自ら草木染めした和紙を捻って絞って作るという人形は「命懸けで作るんや、お産みたいなものやでえ〜」と言っていたそうだ。そうしてできた美しい人形を山岡は、決して手放そうとはしなかった。
実際に話し、交流した人たちによる思い出話は、私の想像をはるかに超えていた。 変わり者で、謎が多い人形作家、という従来のイメージから、人間・山岡草の温かな人間性がわかったし、やはり人形を子どものように思っていたということがはっきりと裏付けられた。あの写真は、まさに親が撮った、遊ぶ子どもたちの記録なのかもしれない。その証拠に「神シリーズ」は、一枚も本人が撮った写真が残ってないのだ。

未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。