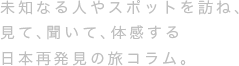100年以上使えて、3年で土に還る―― 信州、大町で生まれる山ぶどう籠バッグ、世界へ羽ばたく
写真= 柳澤聖子(表記があるもの以外すべて)
未知の細道 No.289 |25 September 2025
#6母は洋裁家、父は家具職人
船生さんは埼玉県で生まれ育った。家の中には、いつもミシンの音が響いていた。
「母は製縫の仕事で、オンワード樫山のスーツを請け負っていました。父は家具職人で家具店を営んでいたんです。だから小さいころから“ものづくり“が身近にありました」
小学生の頃まで、船生さんの服はすべて母の手づくりだった。今振り返れば贅沢なことだが、当時は少し恥ずかしかったという。
「友だちは、流行のジャージや既製品の服ばかり。一方、僕は手づくりの服で浮いていたと思います。母には申し訳ないと思いましたが、小学5年生のとき『もう作らないで』と頼んだんです」
やがて雑誌で見た流行の服を着るようになったものの、高校生の頃には既製品に違和感を覚えるようになった。街に出れば、皆が同じような服を着ている。それはカバンも同じだった。
「すごく気に入ったデザインのカバンでも、内ポケットの位置が使いにくいなど、必ずどこか不満が出るんです。自分の好みに完璧に合う既製品はないかもしれないと気づきました。それなら自分で作ればいい――。そうして最初に自分で作ってみたのが革のカバンでした」
バイクが趣味だった船生さんは、荷物を積むためのサドルバッグ作りに夢中になった。一枚の革を裁断しパーツを組み立てるように縫い上げていく作業がおもしろく、のめり込むうちに技術も磨かれた。ある日、船生さんのサドルバッグを見た知人の店主から、「これは、どこで買ったの?」と声をかけられた。自作だと伝えると「ぜひうちで売らせてほしい」と言われ、革製品の販売を始めることにした。
当時の船生さんは運送会社で働きつつ、いつか自営業として独立する夢を追いながら資金を貯めていた。他にも調理師、カメラマンなど、稼げる仕事なら、なんでも挑戦したという。やがて革製品を販売するうちに自信がつき、1993年、23歳のころ革細工作家として独立した。
船生さんのサドルバッグはとても独創的だった。一般的なサドルバッグは20点ほどの革パーツで作られるのに対し、船生さんは240点ものパーツを組み合わせて仕上げたという。
「遊び心も大切にしていました。壊れやすい場所には、こっそりと“修理はコチラにお電話ください”と刻印を入れたり、端材で作ったオセロを隠したシークレットポケットを仕込んだり。お客さんが気づいて、喜んで手紙をくださったこともありましたね」
バイク雑誌で船生さんのサドルバッグが紹介されると注文が殺到したが、革細工作家で生計を立てるのは難しかった。革1枚の仕入れに7~8万円。1つの製作には1カ月近くかかる。20万円で販売しても、利益は月十数万円にしかならない。受注が1年半待ちとなり、限界を感じた船生さんは、独立から3年で作家をやめる決断をした。

未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。